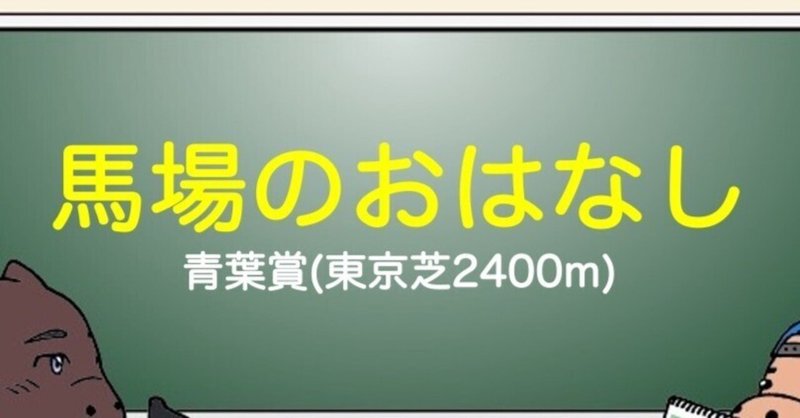
【青葉賞2024】東京芝2400mの特徴と馬場傾向(トラックバイアス)
青葉賞の好走傾向=馬場差無

直線平均進路:5.2頭目÷大外平均:11.2頭目=馬群内直線位置:46%
4角平均位置:7.1番手÷出走平均数:16.2頭=馬群内道中位置:44%
好走馬上がり3F平均タイム=34.53秒
日本ダービーに向けたステップレース。皐月賞までに賞金が加算できなかった馬、中距離系のスピードへの対応力に不安のある馬がここで勢いをつけて本番を目指す。
好走馬の傾向は内外が平均進路5.2頭目(46%)、脚質は4角平均位置7.1番手(44%)と共に真ん中に限りなく近くほぼフラットな数値。枠順成績を見ると目立った傾向は見られない。
上がり3Fのタイムは34.53秒、上がり上位が毎年好走しているため4角の位置に関わらず末脚に長けた馬が好走していることがわかる。
日本ダービーと同舞台異展開

東京競馬場で最も格の高いレースは日本ダービーとジャパンカップと評価する人が多い。それは各馬がこの舞台を目指し生産されているというものもあるが、コース形態自体にもその理由がある。
スタートから最初のコーナーとなる1角までは350mとそれほど遠くない。本来ならばスタートと最初のコーナーが近いと自然と内枠有利になりやすいが、コース全体の傾向では内外に強い傾向はない。それは日本で最も円周の大きなコースで、アップダウンはそれほど激しくなく、さらには直線が525mで長い上に広いために、コース形態的にどの馬にも好走のチャンスが生まれるフラットな舞台である。
フラットの舞台だからこそ、そのレース自体の特徴が色濃くでる。

青葉賞と日本ダービの過去10年枠順別成績を比較する。どちらとも比較的内枠の方が成績が良いように見えるが、二つを比較すると日本ダービーの方がより内枠に良績が集まる。
青葉賞は春の東京開催開幕2週目、日本ダービーは開幕6週目で、常識的にいうと開幕間もない青葉賞の方が内側が綺麗な状態のはず。しかしながら現象が逆転しているのは2点の理由が挙げられる。
①ペースの違い

日本ダービーは全てのホースマンが目指すと言われるGⅠの中でも格式高い特別なレース。出走全馬一生に一度しか出ることのできないレース。反対に青葉賞は同じく世代限定戦ではあるものの、当然ながら日本ダービーとは位置付けが異なるステップレースの重賞。本番と同じ舞台ながらここをステップに日本ダービーを勝利した馬は20年遡っても0頭、最高は2着まで。
これはラップにも現れ、日本ダービーは本番らしく中盤で速いラップを刻むのに対し、青葉賞はトライアルらしく息の入った山なりラップとなる。それぞれの加速点は異なるものの日本ダービーの方が加速度合いが鋭く、青葉賞の方が若干緩いだろうか。
後半5Fだけで見ても、日本ダービーが58.95秒に対し、青葉賞は59.24秒で若干遅いのも違いと言えるだろう。
周回コースにおいて、ペースが速いと外を走る馬はコーナーを経る度に遠心力を受けてしまうため不利になってしまうが、緩んだ分だけ馬群が恐縮して終盤の末脚で突き抜ける可能性が高くなる。
日本ダービーに比べて緩い展開になりやすい青葉賞だからこそ内枠ばかりに良績が集まらないのではないか。
②コースマネジメント

春の東京開催は全10週のロングラン。コースは仮柵を移動させ4つを使い分けて内側の傷みを軽減させていく。青葉賞が行われるのは4月4週目でAコース2週目、日本ダービーが行われるのは5月4週目でCコース(=コース替わり)である。日本ダービーが開催される週から仮柵が移動をするため、それまで多くの馬が走っていた内側の走路は仮柵によって隠される。
また内外だけでなく馬場の硬さにも変化がある。春の東京開催は開幕前にエアレーション作業を施すことが通例。開幕前のエアレーション作業は馬場が柔らかく解された状態で開幕を迎えること以外に、開催が進むと馬場が踏み固められていき後半になるにつれて馬場が硬くなっていく特徴がある。開幕当初の青葉賞の頃は馬場がまだ柔らかく外を走る差し馬にもチャンスがあるが、開催の真ん中に差し掛かる日本ダービーの頃には馬場がある程度踏み固められているために内を走る先行馬に利が生まれやすい馬場状態になるのだ。
以上2つの理由が馬場的に青葉賞と日本ダービーの傾向を異なった形にしているのではないかと考える。
前走距離からわかる路線設定

青葉賞の過去10年前走距離別成績を見ると、同距離からの参戦が最も良績で、距離が短くなる毎に成績を落としている。これはコースやレースが距離延長組に不利なのではなく、ここに挑んでくる≒勝機のある馬は元々短い距離に適性がない、実力が足りない、視野に入っていないような馬ばかりであるということだ。
2000mまでで実力・実績があれば素直に皐月賞やそれに準ずる重賞に向けて調整すれば良い。しかしながらこの舞台に駒を進めて日本ダービーへの出走権、好走を目指すのならば初めから長めの距離に焦点を合わせる馬が自然である。
当週の馬場傾向
<トラックバイアス>
2017年 土曜:6.2/日曜:6.5
2018年 土曜:5.3/日曜:8.1
2019年 土曜:5.6/日曜:6.2
2020年 土曜:5.0/日曜:6.6
2023年 土曜:5.3/日曜:4.9
※数値はその日の3着内馬がL1Fで内ラチから何頭分離れた場所を走ったかの平均値
開催2週目に当たるため馬場傾向は比較的内に好走馬が集まっている。今年は先週日曜に雨が降ったものの大きな影響はなかったようで例年通り~若干マイルドで内外に差がないくらいで推移した。
注目馬
◎ショウナンラプンタ
新馬戦2000mで下ろし、前走2400mを勝利している臨戦過程から、まさにこの距離にターゲットを絞り青葉賞で好走するようなタイプの長距離系クラシックタイプの馬。さらに毎度上がり上位になるだけの末脚を兼ね備え、ある程度流れてある程度末脚が求められるこのレースには相性が良さそうだ。
主戦を務める鮫島克駿騎手が常々「いい馬」「大きい舞台でやれる馬」とコメントを残すほど認めていて、課題はゲートや折り合いなど様々あるものの、前走はそれをしっかり乗り越えて見事勝利して成長を感じる。
新馬戦では京都2歳S③着のサトノシュトラーセを千切っていて実力は確かである。長い距離になって重賞制覇、日本ダービー出走権獲得を期待する。
★最終予想はX(旧Twitter)で公開予定です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
